tel: 045-232-4956
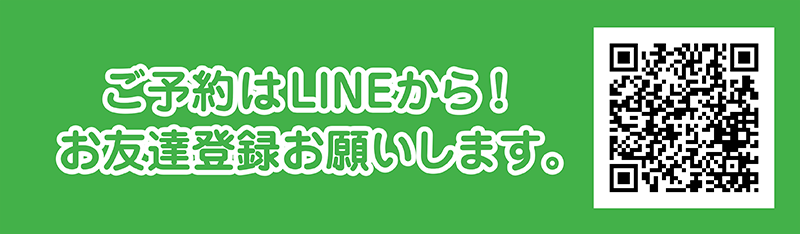

頭痛対策
気象変化に負けない頭痛の予防法と対策
台風や低気圧の時に頭痛に悩むことはありませんか?実は頭痛にはさまざまな種類があり、その中には気象病と呼ばれるものが存在します。気象病は気候や天気の変化が原因で起こる体調不良の総称です。
8月は台風が活発に発生する時期。台風は気圧の変化が大きいので、この時期、症状に苦しめられる方も多いのでは?
ここでは、そんな頭痛の原因や症状、予防方法、対策などについて詳しく解説します。

頭痛の原因とは?
自律神経の乱れが頭痛の原因となることがあります。
自律神経は、交感神経と副交感神経という2つの部分から成り立っており、それらがバランスよく調節することで体の様々な機能が自動的に制御されています。
頭痛は、気圧の変動や湿度の増加によって引き起こされることが多く、これらの気象条件の変化が自律神経に影響を与えることが考えられます。
気圧の変動
台風や低気圧の接近による急激な気圧の変化が頭痛を引き起こす原因とされます。気圧の低下によって脳血流が変動し、血管の収縮・拡張が起こるためです。
湿度の増加
湿度が高い日の過ごし方によって頭痛が発生することがあります。湿度が高いと体内の水分調節が妨げられ、脱水症状による頭痛が起こる可能性があります。
温度の変化
気温の急激な変動や高温多湿な気候が頭痛の原因となることがあります。気温の変化に対応するために、体が過度にストレスを受け、頭痛を引き起こすことが考えられます。
季節の変わり目
季節の変わり目は気候の不安定さが高まり、頭痛を誘発する要因となることがあります。特に気象の変化に敏感な方は、季節の移り変わりに頭痛が増えることがあります。
頭痛の症状
-
● 頭痛やめまい
頭部に圧力や重さを感じることで頭痛、めまいやふらつきが現れることがあります。
-
● 頭重感
気象の変化によって頭部に重たさを感じる症状を頭重感といいます。頭部がぼんやりとした感覚で満たされることもあります。
-
● 集中力の低下
気象病による頭痛が強いと、集中力の維持が難しくなりして仕事や日常生活に支障をきたすことがあります。
-
● 倦怠感
強い頭痛やそれに伴う体内の不調により、倦怠感が生じることがあります。また、体力の消耗や気力の低下を感じることもあります。
頭痛の予防方法
◇ 快適な室内環境を保つ
気圧の変化が影響を及ぼすことが多いため、室内の温度や湿度を快適な範囲に調整することが重要です。エアコンや加湿器・除湿器を使用して、過ごしやすい環境を保つようにしましょう。
◇ 耳の温め
耳の後ろには完骨(かんこつ)と呼ばれるツボがあります。頭痛の起きやすい方は、日頃より耳後ろにある完骨周辺を温めることをおすすめします。

◇ 水分補給
健康的な食事や十分な水分摂取が重要です。特に気象の変化によって体調が不安定になるときは、水分補給やバランスの取れた食事を心掛けましょう。
◇ 適度な睡眠
適度な睡眠時間を確保することで、体調を整えることができます。不規則な生活や寝不足は頭痛を悪化させる可能性がありますので、日頃より規則正しい生活リズムを心掛けましょう。
頭痛の対策
-
頭痛薬の使用
軽度の頭痛の場合は市販の鎮痛剤を使用することができますが、頭痛が慢性的になっている場合や、頻繁に起きる場合は医師に相談して適切な処方薬を受け取ることが重要です。

-
食生活の改善
不規則で栄養の偏った食事は自律神経を乱し頭痛を引き起こす可能性があります。体内の水の巡りをサポートするために、豆類や海藻類を積極的に摂るようにしましょう。また、ビタミンB群やマグネシウムの不足は自律神経の調整に影響を及ぼす可能性があるため、お肉や緑黄色野菜や乳製品もバランスよく摂るようにしましょう。

-
休息とリラックス
頭痛が起きたら、できるだけ早めに休息を取り、リラックスすることが大切です。静かな場所で目を閉じ、深呼吸をし、リラックスを心がけましょう。慢性的に頭痛が続く場合はクリニックの受診をおすすめします。

-
運動療法
気象病による頭痛症状をお持ちの方は内耳が過敏になっていることがあります。耳や耳周囲の血行改善のために、運動療法を行うことが有効です。また、自律神経を整えるためにも日中はアクティブに動くことが大切です。起床時に朝日を浴び、しっかり朝食を取り、適度な運動を心がけましょう。休息とリラックスと上手くバランスを取っていきましょう。

-
頭痛安眠矯正
当院の頭痛安眠矯正は不眠による頭痛の改善効果があります。自律神経を整えることで、頭痛改善を期待できます。なお施術中はアロマを使用し、リラックスしていただけるようにしています。
当院の頭痛安眠矯正についてはコチラ
気圧や気候の変化から起こる頭痛に関しては個人差があり、自己判断だけで解決することは難しいかもしれません。もしも頭痛が発生してしまった場合は無理せず休息を取り、その後は心身のリラックスとバランスのよい運動を心がけましょう。
なお、症状が長く続く場合は専門家のサポートを受けるようにしましょう。当院でもアドバイスや治療を行っておりますので、お悩みの方は一度当院へお越しください。
